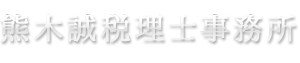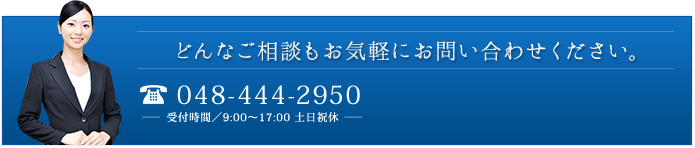給与から徴収される税金
2年目から手取りが減る?
新卒で入社した方は、この春が初任給という方も多いでしょう。日経新聞がまとめた2026年度採用計画調査によると、物価上昇を背景にしてか25年度の初任給を30万円以上とする企業が24年度から倍以上に増えたそうです。
給与から徴収される税金は「所得税」と「住民税」ですが、住民税については昨年1~12月の所得や控除で今年6月からの住民税が計算されるため、新入社員の1年目の給与からは学生時代のアルバイト量がよほど多くない限り、住民税が徴収されません。2年目6月の給与から、1年目の所得や控除に応じて住民税が天引きされるようになるため、手取りが減るという現象が発生します。初任給から2年目の給与が10%以上増え